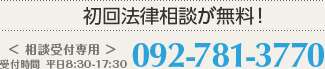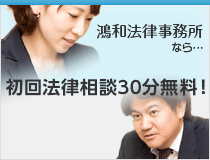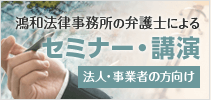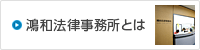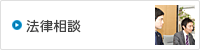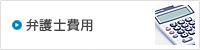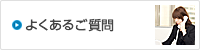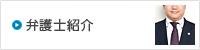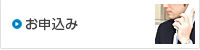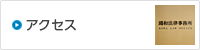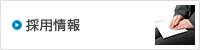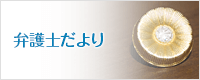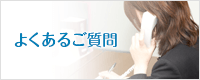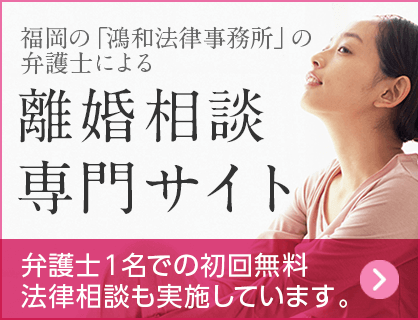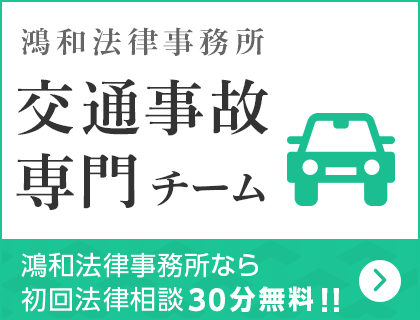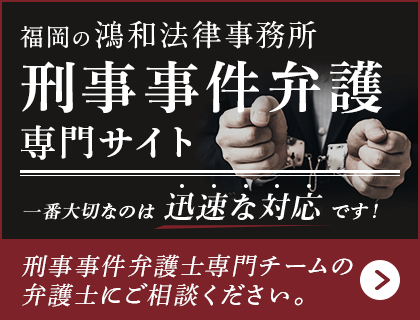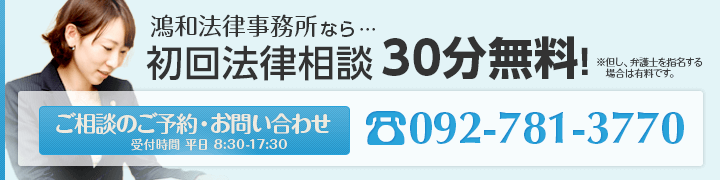事業譲渡・職種廃止と雇用・配置転換命令
2025/01/06弁護士の是枝(これえだ)です
新年を迎え、「今年は新たな事業に挑もう」と決意する経営者もいらっしゃるだろうと思います
もっとも、事業譲渡のご相談をお受けするなかで、雇用のに関する意識が希薄に感じられることがあります
また、昨年は、職種限定合意における同意なき配置転換を違法とする、注目すべき最高裁判決も出ています
そこで、長文ながら設例と対応について書いてみました
【設例1・事業譲渡と雇用】
福岡県の建築業者X社がS社から熊本県の飲食店Aの事業譲渡を受ける方向で、X社とS社が交渉中である
(なお、X社とS社は無関係で実質的同一性はない)
S社は飲食店事業AにおいてY1~Y3の3名を正社員として雇用している
X社は、事業譲渡の際、Y1とY2を雇用したいものの、Y3を雇用したくない
【設例2・職種廃止と配置転換命令】
設例1で事業譲渡を完了したが、2年後、業績不振のため、X社は他社へ飲食店Aを事業譲渡しようとした
しかし、買い手が見つからなかったため、X社は飲食店Aを廃業することとした
そして、X社は、Y1とY2に、X社の飲食店Aの廃業後はX社の本業の建築部門で働くように命令した
Y1は、X社へ、生粋の料理人で建築業界の経験が一切ないことを理由に、上記命令を拒否している
【設例1の前提】
・事業譲渡と労働問題
事業譲渡の定義は、少々難解ですが、通常、「一定の営業目的のため組織化され有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部の譲渡」とされています
飲食店の事業譲渡であれば、建物(または賃借人たる地位)、建物附属設備、什器備品、屋号、許可届出、雇用契約等を一体として譲渡することが多いでしょう
(なお、事業譲渡でも許可・届出の承継が可能です)
これに対し、建物(または賃借人たる地位)、建物附属設備、什器備品等のみの譲渡は、店舗や事業としての一体的な譲渡ではないため、居抜譲渡・造作譲渡と呼ばれており、事業譲渡と区別されます
ただし、現実には事業譲渡と居抜譲渡・造作譲渡とが明確に区別されていないことがあります
また、飲食店の運営母体の株式会社の株式の譲渡は、株式譲渡と呼ばれており、事業譲渡と区別されます
事情譲渡ではなく居抜譲渡や造作譲渡であることが明確であれば、雇用契約の承継は含みませんので、譲受人(設例X社)と譲渡人従業員(設例Y1~Y3)との間での労働問題は、通常、起こりません
株式譲渡であれば、運営母体(設例S社)の株主が譲渡人から譲受人(設例X社)へ変更されただけですので、運営母体(設例S社)と譲渡人従業員(設例Y1~Y3)との間での労働問題は、通常、起こりません
事業譲渡であれば、雇用契約の承継が対象になることもならないこともあるので、譲受人(設例X社)と譲渡人従業員(設例Y1~Y3)との間での雇用等をめぐってトラブルが発生することにあります
・厚労省の事業譲渡指針
事業譲渡における労働契約の取り扱いについて、以下の告示がありますので、事業譲渡を検討している方は一読しておくと良いでしょう
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(平成28年厚生労働省告示第318号) ※ PDF
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000630107.pdf
「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が 留意すべき事項に関する指針」の概要 ※ PDF
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/dl/01e.pdf
【設例1について】
・設例1における問題1
まず、X社はY1やY2を雇用できるでしょうか
Y1~Y3は事業譲渡の当事者ではありませんので、Y1やY2の承諾等が必要になります
雇用する方法としては、3つの方法が考えられます
①全員承継合意+承諾
事業譲渡契約において全員の労働契約承継も含めたうえ、X社がY1やY2の承諾を得る方法
②一部承継合意+承諾
事業譲渡契約において一部の労働契約承継も含めたうえ、X社がY1やY2の承諾を得る方法
③承継合意なし+新規採用
事業譲渡契約において労働契約承継を一切含めず、X社とY1やY2の間で雇用契約を新規締結する方法
上記①~③のいずれか判然としない場合、黙示の合意として上記①と判断されることがあります
上記①や②と上記③の違いは、X社とY1やY2の間の雇用契約が、S社とY1やY2の間の雇用契約から、影響を受けるか(退職金や時間外賃金未払、職種限定合意等を承継するか)という違いがあります
X社にとってS社とY1やY2の間の雇用契約の影響がコストやリスクなら、上記③の方法を前提にします
X社にとってY1やY2の雇用が飲食店Aの事業継続に重要であれば、上記①や②の方法を前提に、事業譲渡契約においてY1やY2がX社へ承諾することを契約効力発生条件(停止条件)とすることもあります
(退職金等のコストやリスクは、事業譲渡の代金減額等により、対応することになります)
なお、上記①~③のいずれの方法にせよ、Y1やY2がX社へ承諾等しなかったからといって、S社からX社への事情譲渡を理由にS社がY1やY2を解雇することは当然にはできませんので、注意が必要です
(S社のY1やY2の解雇は、整理解雇となるため、整理解雇の要素を満たす必要があります)
・設例1における問題2
次に、X社はY3の雇用のみを拒否できるでしょうか
前記①の方法(全員承継合意)の場合で、Y3がX社へ労働契約承継に承諾しているときは、X社がY3の雇用のみを拒否することは、実質的な解雇にあたりかねず、当然には拒否できないものと考えられます
前記②の方法(一部承継合意)の場合で、Y3がX社へ労働契約承継に承諾しているときは、X社がY3の雇用のみを拒否することは、一応可能であると考えられますが、拒否できない場合があり、注意が必要です
すなわち、上記②の方法(一部承継合意)でも、Y3が労働組合に加入していることを理由として拒否すると、不当労働行為として無効となる(X社かS社からS社とY3の間の労働契約を承継する)ことがあります
また、上記②の方法(一部承継合意)でも、労働契約承継前または後に労働条件の切り下げに同意しないことを理由して拒否すると、実質的な解雇にあたりかねず、当然には拒否できないものと考えられます
前記③の方法(承継合意なし)の場合で、Y3がX社へ雇用契約新規締結を希望しているときは、X社がY3の雇用のみを拒否することは、基本的には可能であると考えられますが、注意は必要です
前記③の方法(承継合意なし)であっても、設例と異なり譲受人がほぼ全員の労働者を採用したがごく一部の労働者を不合理な理由で採用しなかった等、実態に照らして、全員承継合意と判断されることがあります
・設例1に関する補足(商号続用や屋号続用等)
商号とは、商人が営業を行う際に自己を表示する名称のことを言います
商人が会社であれば、商業登記に商号が登記されています
例えば、株式会社X建設であれば、「株式会社X建設」が商号です
これに対し、屋号とは店舗や事業の名称のことを言います
屋号は商号を用いることもあれば違うものを用いることもあります
例えば、株式会社X建設運営の飲食店Aなら、「A」が屋号です
設例とは異なりますが、X社がS社から飲食店Aの事業譲渡がなされる際、もしX社が商号を「X」から「S」へ変更する場合(商号続用)には、注意が必要です
この場合には、商法17条1項により、飲食店Aに関してS社が取引先や従業員に対して負う債務について、X社も取引先や従業員に対して債務を負うことがあります
なお、免責登記や免責通知により商号続用責任を回避することができます
設例のように、X社がS社から飲食店Aの事業譲渡がなされる際、飲食店において「A」という屋号を使用し続けた場合(屋号続用)にも、注意が必要です
この場合には、商法17条1項の類推適用により、飲食店Aに関してS社が取引先や従業員に対して負う債務について、X社も取引先や従業員に対して債務を負うことがあります
なお、免責登記や免責通知により商号続用責任を回避することができます
商号続用や屋号続用の場合以外でも、事業譲渡の際の債務引受広告による債務引受(商法18条)、詐害事業譲渡にかかる債務履行請求(商法18条の2)の制度があります
事業譲渡は、本来、譲渡人と譲受人の間の自由な契約による債権契約・特定承継であり、契約当事者以外に影響しないはずです
しかし、実態として取引先等の事業自体に対する信頼がある以上、一定程度保護すべきものとされています
【設例2の前提】
・配置転換命令権(配転命令権)
配置転換(配転)とは、同一企業内における職務内容や勤務場所を変更することを言います
使用者に配転命令権があれば、労働者の個別的な同意なしに、配転命令ができますし、使用者に配転命令権がなくとも、労働者の任意性・真意性のある個別的な同意があれば、合意により配置転換ができます
まず、配転命令権は、当然に認められるものではなく、次の全ての要件を満たす必要があります(判例)
就業規則等の配転命令に関する包括規定
労働者の頻繁な転勤・配置転換の実態
勤務地限定合意や職種限定合意の不存在
次に、配置転換命令は、次のいずれかの場合には、権利濫用となるため、認められません
業務上の必要性がない
不当な動機・目的をもってなされる
通常甘受すべき限度を著しく超える不利益を負わせる
・職種限定合意
職種限定合意とは、使用者と労働者との間の職種(業務内容)を限定する合意を言います
最近の判例で、黙示の職種限定合意を認定して、配置転換命令を権限なしで無効としたものがあります
※ 最判令和6年4月26日(判タ1523号80頁)
裁判所ウェブサイト該当判決
【設例2について】
X社はY1へ配置転換命令違反として処分や解雇等をすることが考えられますが、可能でしょうか
・配置転換命令権(配転命令権)の有無の検討
設例では明らかではありませんが、「就業規則等の配置転換命令に関する包括規定」等の要件を満たしていないのであれば、配転命令権がないことになります
・職種限定合意の有無の検討
職種限定合意があれば配転命令権はありません
まず、雇用契約や就業規則に職種限定合意が明示されていれば、職種限定合意があることになります
設例では明らかではありませんが、設例1で労働契約承継があったならS社とY1の間の労働契約の内容を、設例1で労働契約承継がなかったならX社とY1の間の新規契約の内容を、確認することになります
次に、雇用契約や就業規則に職種限定合意が明示されていない場合、どのように考えるべきでしょうか
実態に照らして黙示の職種限定合意を認定することについて、以前の裁判所は慎重であったようですが、最近の判例(前掲最判)は認定しているため、今後は認定される傾向になるものと思われます
設例では、次の事情があるため、黙示の職種限定合意を認定される可能性があります
事業譲渡以前(期間不明)、Y1はS社から飲食店Aの正社員として雇用されていたこと
事業譲渡以降の2年間、Y1はX社から飲食店Aの正社員として雇用されていたこと
X社の建築部門と飲食部門の関連や交流が乏しいこと
Y1は生粋の料理人で建築業界の経験が一切ないこと
・職種限定合意(黙示含む)があった場合の対応
職種限定合意(黙示含む)があった場合、X社のY1等の従業員に対する配転命令権はないことになります
そのため、配転命令違反が成立しない以上、X社がY1を配転命令違反として処分することはできません
なお、上記にもかかわらず、配転命令を出し続けたり配転命令違反として処分したりすると、違法無効な命令や処分によるハラスメントとされて、X社はY1から損害賠償請求を受ける可能性があります
X社としては、Y1へ、職種廃止の経緯や雇用維持の意義等を説明したうえで、配置転換に同意するよう、任意性・真意性を害しない程度に説得することになりますが、簡単ではないものと思われます
最終的には、整理解雇に準じて、退職金の加算などによる希望退職の募集・打診、解決金の支払を伴う退職勧奨を経たうえで、退職に至らない場合には、最終的には整理解雇を行うことになるものと思います
【おわりに】
以上のとおり、事業譲渡時の雇用や職種廃止時の配置転換は、思いのほか労働問題に発展しやすいものです
新規事業がうまくいくかに目が行きがちですが、雇用が絡むため、先々を見据えた判断が重要です
長文にもかかわらずお読みいただきありがとうございます
令和7年1月6日
文責 弁護士 是枝秀幸(これえだ・ひでゆき)