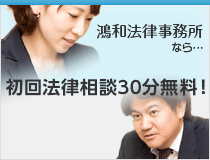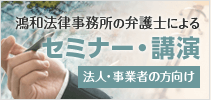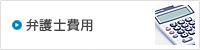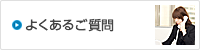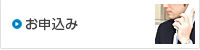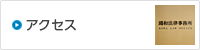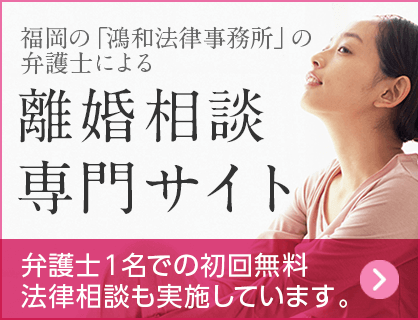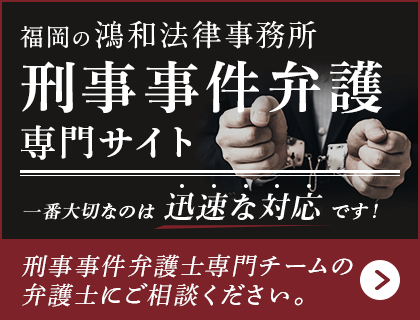成年後見制度を利用して財産を守ろう!
2014/02/271 成年後見制度とは?
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人を法律的に保護し、支えるための制度です。
本人が認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分であり、自分の財産を適切に管理することができない場合に、成年後見人等が、本人に代わって、医療や介護に関する契約を結んだり、預金の払戻しや解約の手続きを行い、本人の財産を適切に維持・管理し、本人に不利益が及ばないように保護しようというものです。
(1)成年後見制度の概要
成年後見制度は、「後見」、「保佐」、「補助」の三つに大別され、本人の判断能力の程度によって類型が異なります。例えば、日常生活の買い物で釣銭の計算すら困難な程判断能力がほとんどない場合は「後見」に該当します。どの類型に該当するかによって本人単独でできる行為の範囲が異なりますが、どの類型に該当するかは医師による鑑定の結果を踏まえた上で裁判所が判断することになります。
以下、「後見」、「保佐」、「補助」の各類型について簡単に紹介します。
(2)成年後見
成年後見が始まると、本人の預貯金や不動産の管理、年金や保険金の受領、契約の締結等、財産に関する全ての法律行為について、成年後見人が本人に代わって行うことになります。本人が勝手に不動産を売却してしまった場合等も、成年後見人は契約を取り消すことができます。
(3)保佐
保佐は、日常の買い物程度であれば本人ひとりで行うことができるが、不動産の売買や自動車の購入といった重要な財産の契約等を行うことが困難な場合に開始されます。
その場合、民法に定められた行為(不動産取引や預貯金を払い戻すことといった重要な財産を処分する行為が定められています。)については、保佐人の同意が必要となりますし、保佐人の同意なく本人が勝手に行った行為は契約を取り消すことができます。場合によっては、裁判所が定めた範囲の行為については、本人に代わって、保佐人が行うこともできます。
(4)補助
補助は、不動産の売買や自動車の購入といった重要な財産の契約等を本人ひとりで単独で行うことができるかもしれないが不安なことが多いといった程度の判断能力のときに開始されます。
日常生活上は特に問題がないことが多いため、本人ひとりで行うことができる行為の範囲は保佐の場合よりも広く、裁判所が定めた特定の行為に限って補助人が援助することになります。
2 成年後見制度の利用のメリット
このように、成年後見制度は、成年後見人等が本人に代わって財産を適切に管理するため、本人が業者の執拗な勧誘によって高額商品や投資性の高い金融商品を買わされたりすることを未然に防ぐことができますし、病院や施設への入院・入所契約といった必要な行為もスムーズに行うことができます。
また、一般的な家族では、わざわざ成年後見人等を就けることなく親族が事実上財産を管理することはよくあることかと思いますが、本人が亡くなり相続が開始すると、「もっと財産が残っているはずだ!」などと生前の使途不明金を巡って相続人間で争われることも少なくありません。
成年後見制度を利用すれば、成年後見人等は本人の財産の収支を裁判所に報告し裁判所が後見的に監督するため、そのような紛争を未然に防ぐことができます。
3 成年後見人等の選任方法
(1)成年後見人等を就けるには、まず、家庭裁判所に成年後見等の申立てを行います。申立ては、配偶者や4親等内の親族(親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこ、本人の配偶者の親、子、兄弟姉妹)が行うことができます。
申立て自体は配偶者や親族等が自身で行うこともできますが、申立てには、戸籍謄本や住民票の他、預金通帳の写しや不動産登記簿謄本等、必要書類一式を添付した上で、必要事項を記載した書式で申し立てる必要があります。慣れていないとなかなか大変なものですが、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として申立てを行うことができます。
(2)誰が成年後見人等に就任するかは、本人の心身の状態、生活状況、財産状況、候補者の職業・経歴、候補者と本人との利害関係の有無、本人の意向等を踏まえて、裁判所が総合的に判断して決定しますが、親族が就任するケースもあれば、法律や福祉等の専門的知識が必要な場合には弁護士や福祉関係の専門家が選任されるケースもあります。一旦、成年後見人等に選任されると、原則として、本人が亡くなるか判断能力を回復するまで続き、裁判所への報告等の責任も生じますので、本人が不動産や預金、保険等、多額の財産を所有し、事務量が比較的多い場合には、弁護士等の専門家に任せる方が安心でしょう。
4 成年後見制度は本人の財産を適切に管理するための制度であり、利用することによって紛争を未然に防ぐことにもつながります。
本人やご家族が安心した生活を送るためにも、成年後見制度の利用を一度検討されてはいかがでしょうか。
平成26年2月27日
文責 弁護士 大塚祐弥