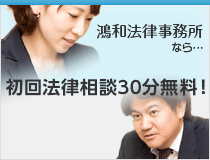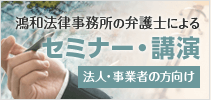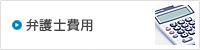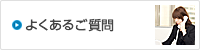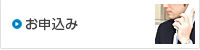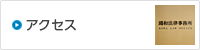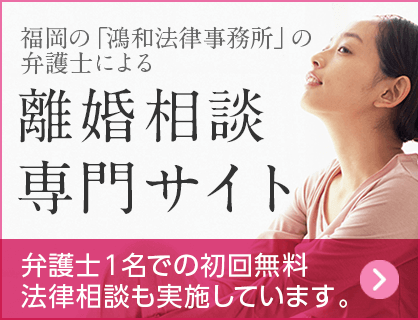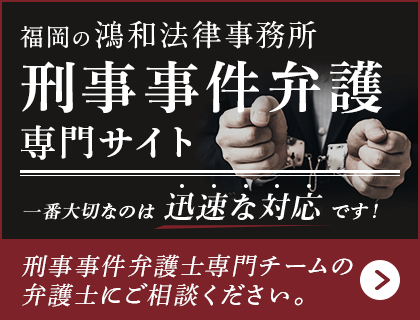少年法改正で18歳・19歳の少年事件はどう変わるのか
2022/01/13昨年(2021年)5月、少年法が改正されました。
選挙権や民法上の成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、少年法の適用年齢も18歳未満に引き下げるべきではないかとの問題提起がきっかけで議論された法改正ですが、最終的には18歳及び19歳の少年についても少年法が適用されることになったものの、「特定少年」として18歳未満の少年と大きく取り扱われ方が変わることになりました。
まず、18歳及び19歳の「特定少年」も、少年法が適用されることは変わりありません。
犯罪(非行)をした疑いがあれば捜査機関が捜査をし、検察官が家庭裁判所に事件を送致します。捜査段階では警察署の留置所で逮捕勾留されることもありますが、家庭裁判所に送致された後は、釈放されなければ少年鑑別所に移されることになります。
なお、18歳未満の場合、実際には犯罪(非行)をしていなくても、性格や環境に照らして将来犯罪をするおそれがある場合には、「虞犯(ぐはん)少年」として家庭裁判所に送致され保護処分を受けることがありましたが、18歳・19歳の少年については「虞犯少年」として家庭裁判所に送致されたり処分を受けたりすることはなくなりました。
その後、家庭裁判所調査官による調査や少年鑑別所による心身鑑別などが行われることも18歳未満の少年と変わりありません。
大きく変わるのは、そのような調査等を経た上での少年審判です。
具体的には、非公開の審判廷で行われるのは18歳未満の少年と変わりませんが、家庭裁判所による決定内容やその判断基準が大きく変わることになりました。
審判が開かれた場合、少年に対しては「不処分」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童養護施設送致」「少年院送致」「検察官送致(逆送)」という決定がなされます。このうち児童自立支援施設と児童養護施設は法律上18歳未満の少年が収容対象となっていてもともと18歳・19歳の少年に対して決定されることはなく、不処分についても特に改正前と変わりはありません。
しかし、それ以外の「保護観察処分」「少年院送致」「検察官逆送」については、決定内容や判断基準が大きく変わりました。
まず、保護観察処分に関しては、原則20歳に達するまでか保護観察所の判断で解除されるまで続くこととなっていたため、家庭裁判所の審判の段階では特に期間を定めることはしていませんでした。
しかし、今回の少年法改正により、審判時に18歳・19歳の少年に対して保護観察処分の決定をする場合には、6か月か2年のいずれの期間とするかを審判時に定めることになりました。
次に、少年院送致に関しては、これまでは収容期間に関しては、「特別短期間」「短期間」「比較的短期間」「比較的長期間」「相当長期間」といった処遇勧告がなされることもありましたが、処遇勧告がないケースが大半で、その場合の少年院の収容期間は1年程度となっていました。
しかし、今回の少年法改正により、審判時に18歳・19歳の少年に対して少年院送致の決定をする場合には、3年以下の範囲内で収容期間を審判時に定めることになりました。
最後に、検察官送致(逆送)は、その犯罪の内容や情状に照らして刑事処分が相当と認められるときの処分ですが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で、事件時に16歳以上だった場合には、原則として検察官送致となるとこれまでは定められていました。
しかし、今回の少年法改正により、事件時に18歳・19歳だった場合には、短期1年以上の罪、たとえば強制性交等罪や強盗罪などの事件でも原則として検察官送致になることになりました。
もちろん、あくまで「原則」であって「例外」もあり、これまでも原則逆送にあたるケースでも少年院送致等になるケースも相当数ありましたし、18歳以上で重い犯罪行為の場合には原則逆送ではなくとも検察官送致になるケースも多くありました。その意味では、今回の少年法改正で実際にどれくらい検察官送致が増えるのか分かりませんが、少なからず影響が出る可能性があります。
検察官送致決定があると、改めて検察官において捜査・検討し、検察官が起訴すれば成人事件と同様に刑事裁判を受けることになり、有罪となれば刑事罰を受けることになります。
これまでは20歳未満の少年に実刑判決を科す場合には、刑期の幅を持たせた不定期刑を科さなければなりませんでしたが、今回の少年法改正により、判決時に18歳以上であれば成人と同様に定められた刑期が言い渡されることになりました。
このように、来年(2022年)4月からは、18歳・19歳の少年事件には様々な変化があり、それに対応した弁護活動や付添人活動が重要になってくると言えます。
甲木真哉